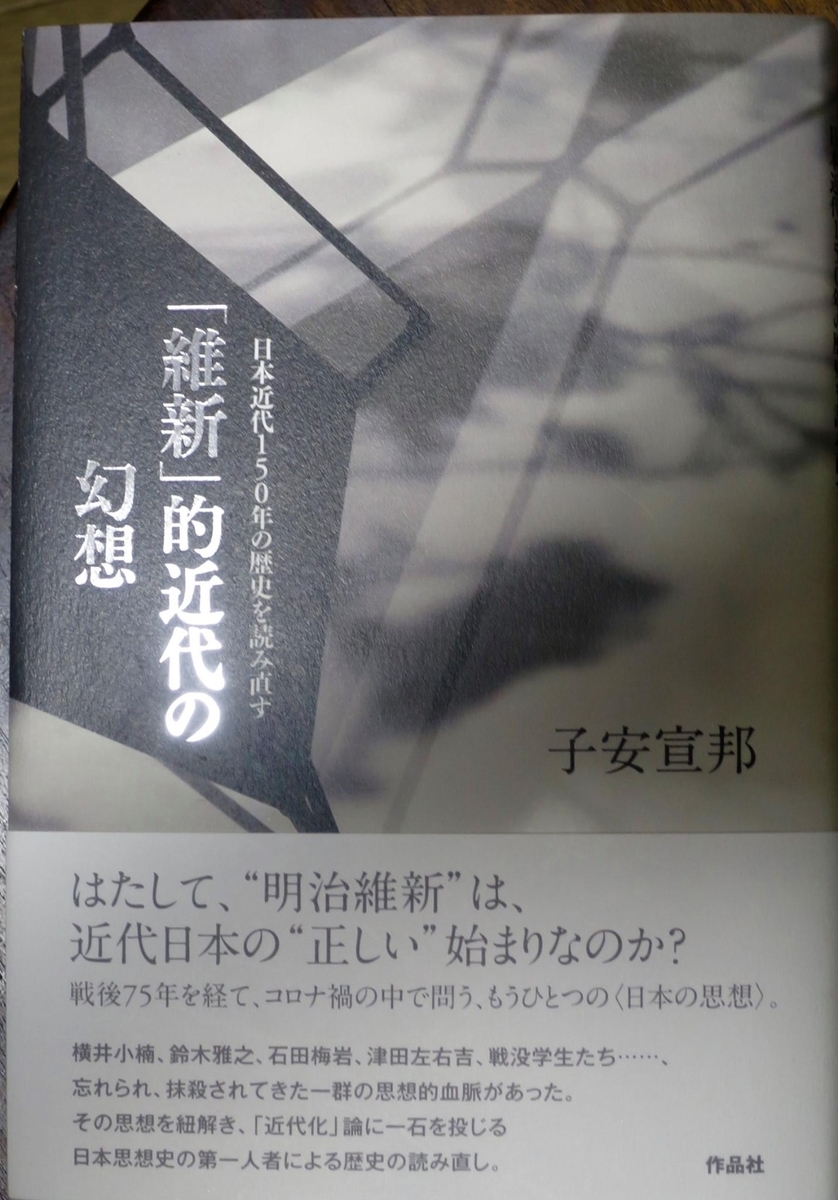書評
子安宣邦 著、 「維新」的近代の幻想、 日本近代150年の歴史を読み直す (作品社)
本多 敬
「『維新』的近代の幻想」とは何であろうか。日本近代150年の歴史を問い直す子安宣邦氏の著書は、外部の思考を失い閉じた内部的幻想に囚われたわれわれが語ることができなくなっている「維新」的近代を語ることを可能にする。はたして、「明治維新」は近代日本の「正しい」始まりなのか。子安氏は、開かれた外部の思考のあり方を問い続けてきた。
「維新」という日本近代の限界を語ろうとしたその瞬間に、限界は炸裂してしまうので、語ることができることと語ることが不可能なこととの距離である、原初的分割ともいえる場所へ再び連れ戻される。この言語の端とも表現できる分割点にわれわれは運ばれるが、その端自体が拡散し始めて、自身が相対化されると、われわれもだれも存在しないように感じる。どのような国でも資本を蓄積した後にヴァリエーションをもって資本主義が成立するが、正しい始まりが論理的に先行しないかぎり、自由に喋れる市民はいつまでも存在しないのではないか、つまり、アジアは経済がどんどん進むが、どうして言論の自由が進まないのかということを「『維新』的近代の幻想」は問うのである。
子安氏は、前著の「大正を読み直す」において、思想史における津田左右吉と和辻哲郎とのあいだの思想的対決を、互いに衝突させる形で展開した。一方、「『維新』的近代の幻想」は、津田左右吉論から始まり、和辻哲郎論と北京大学での講演である「『日本近代化』再考」で終えているのであるが、こうして、思考の迂回的遅れの戦略によって、津田の思想の意味を数百頁後の和辻の思想とその天皇論において考えさせようとしているのではないだろうか。はたして、津田左右吉の「ラディカルモダニズム」とは何か。そして、和辻哲郎は国家と宗教にいかなる関係を打ち立てようと考えたのか。
明治とは何か。そして、この問いに先行しなければならないのは、江戸とは何か、という問いである。子安氏が、日本思想史家としての自己形成はこの問いとともにあったという「日本近代の始まり」という問いである。津田左右吉から和辻哲郎へと繋がる、長くゆっくりした分析の線上に、朱子学の視点、そして、「ポストモダン孔子」の方向で一層の深化が求められる「方法としての江戸」と「方法としてのアジア」、中国語に翻訳された「漢字論」、日本近代文学批判、戦没学生たちの手記についての論考が展開される。津田左右吉と和辻哲郎という二つの極の間に以下の思想家たちが取り上げられる。鈴木雅之、横井小楠、石田梅岩、大熊信行、荻生徂徠と会沢正志、中江兆民、徳冨蘆花、夏目漱石、尾崎秀実、田辺利宏、そして、竹内好。子安氏は、「歴史修正主義的な長期政権による権力の集中と腐敗とがとめどなく大きくなりつつある」「今の絶望を再認識」しながらも、「『維新』的日本の近代150年の歴史の中にそれとの血脈的繋がりを信じたくなるような『本物』はいる」として、横井小楠、中江兆民、尾崎秀実、戦没学生たちに「希望に連なる言葉を見出すことができるかもしれないのだ」、という。
こうして、「『維新』的近代の幻想』」は6つの部と17の章で構成される。これらは、東京と大阪で開かれた市民講座(公民教室)である「明治維新の近代」の論考をまとめたものである。
「『維新』的近代の幻想」は、子安氏がいうところの「解体日本思想史」、つまり、脱構築的方法によって、日本近代150年の歴史を読み直す試みである。歴史を読み直すとは何か。これに関しては、終章の「『日本近代化』」再考」と題した北京大学における講演 (2019.5.25.)の後に行われた、学生との討論会のために用意したメモである「北京大・討議のためのメモ:近代・近代化・近代主義」が参考になる。
「『日本近代』を批判しながら、われわれにおける『現代』を見定め、それに直面するためには『日本近代』がその絶対的な始まりとする『明治維新』を相対化しなければならない。これを絶対的な始まりとする『日本近代』をいかに相対化するかが問われてくる。この世界史的『近代』を相対化するには、それぞれの一国的『近代』を考えることによってである。」
ここでは、世界史的「近代」というグローバルな歴史ともう一つの「近代」である地域的な歴史とを考える必要を語っている。国家(一国的言語主義、一国民主主義)という枠を超えたアジア(漢字文化圏)について、確立したグローバルな見方(大きな歴史)のなかに、それとは別の見方をつくること。言い換えれば、歴史を読み直すために必要となるのは、「明治維新」を絶対的な始まりとする世界史的「近代」の普遍を批判する、外部の思考を要請する他者の視点なのである。フーコーの知の考古学は、現代という時代を構成している論理と解釈について述べているが、「世界史の構造」の柄谷行人氏の論理にとって意味があることが形式化を徹底する他者だとしたら、子安氏の解釈にとって意味があることは方法的思考としての他者である、ということを「『維新』的近代の幻想」から学ぶことができると考える。
「国家を人為の制度的体系とすることは、国家を制作物と見ることである。」(中江兆民 『民約訳解』を読むーその1)
「あとがき」において、「制作の秋(とき)」とは今である、と子安氏は述べている。
「1945年の敗戦とは作り替え可能なものとして国家を見ない民族的、神話的国家観の敗北であったはずです。それは新たな『制作の秋』であったはずです。だが制作の主体となりえなかったわれわれは戦後七十余年のいま歴史修正主義的政権によるもう一度の敗北をさせられようとしています。」「核兵器による最初の犠牲者であり、戦争の敗北者であった日本人を、核兵器禁止条約への署名を拒否する安倍首相はそのことの結果として、人類史における道徳的敗北者にしてしまうのです。われわれはこの屈辱にたえることができません。ほんとうにこれを屈辱だと知れば、「制作の秋」とは今だということを知るはずです」。
「『維新』的近代の幻想」は、21世紀の日本の政治を支配するに至った歴史修正主義的ナショナリズムに対抗するための批判的重石をなすものである。こうして、われわれは国家祭祀と天皇制の問題をも考えることになるだろう。天皇とは、歴史が変わってもいつの時代にも現れる構造であり、象徴性を過剰に超える行い(祀るパロール)を許すと、憲法における国民主権の根本を危機に貶める、という現在の問題であり、日本思想史を見渡しながら、精神の従属をもたらす構造を言語化する思想的課題である。
(了)
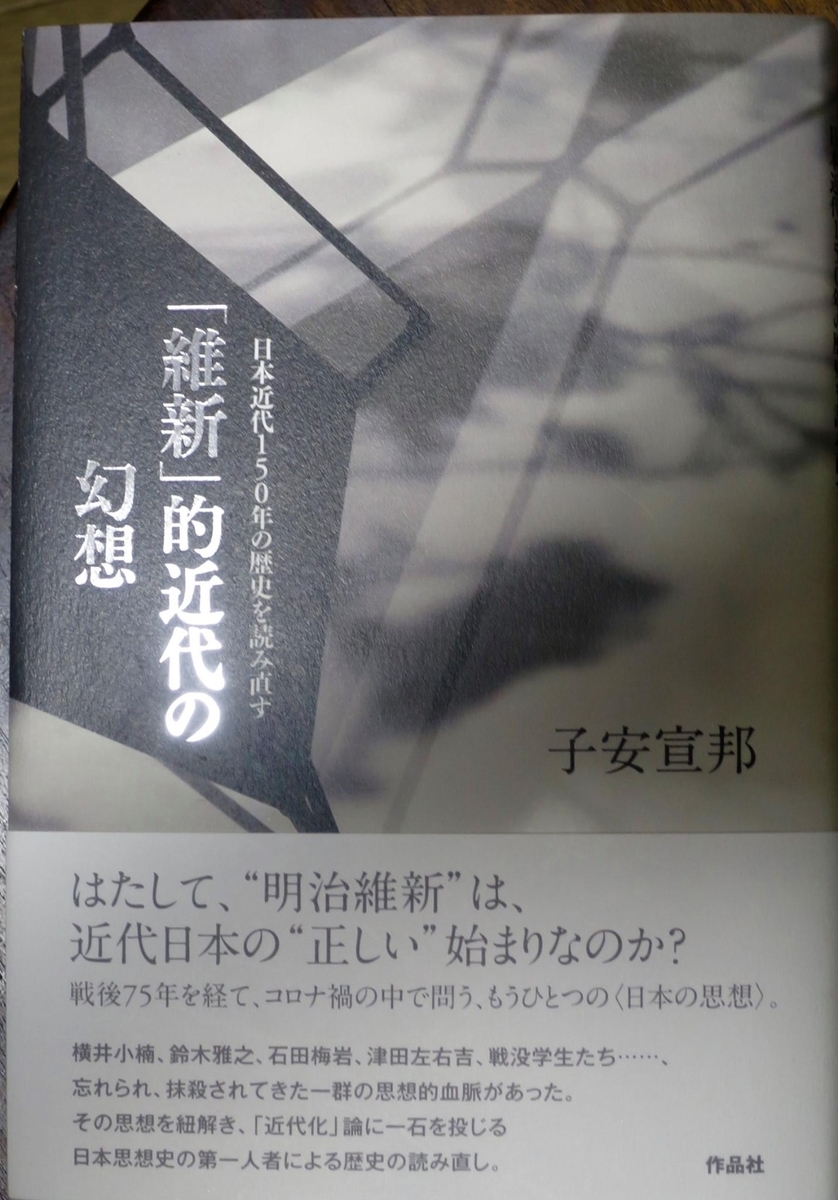
津田左右吉はどのように「明治維新」を語ったか。
「第一章 『王政復古』の維新 津田宗吉『明治憲法の成立まで』を読む」
「いわゆる王政復古または維新が、その実少なくとも半ばは、皇室をも国民をも欺瞞する彼等(イワクラ・オオクボら)の辞柄であり、かかる欺瞞の態度を彼等が明治時代までもちつづけてきた証跡が見える。」
さて、津田左右吉が「王政復古」と呼ぶものはなんであろうか。子安氏はつぎのように説明する。「『王政復古』とは『明治維新』という近代世界に向けての日本の変革を方向づけ、性格づけていった重要な政変である。」「薩長両藩の討幕派という武力的政治集団による政権奪取の政変であった。それゆえこの政変を歴史家は『王政復古クーデター』ともいうのである。」 政権奪取者は、便利なスローガンともいうべき神話を利用して、その神話としての「明治維新」を自らに都合よく政治的に現実化した。 「『王政復古』が武力討幕派によるクーデターであるならば、『王政復古』とはその政権奪取の政変を正当化し、慶喜ら公議政体派を政治的にも屈服させる政治的理念的な標語だということになる。たしかに神武創業という神話的古代への回帰をいう『王政復古』とは、この政権奪取者たちにとって理念的にも、また現実的にも最も望ましい政治標語であったであろう。なぜなら『王政復古』という神話的理念の政治的現実化は、すべて政権奪取者の恣意に任せられることになるからである。」 政権奪取者が行った神話としての「明治維新」の政治的現実化が、それを「王政復古」として覆い隠し、われわれが近代化の別のあり方を考えることを不可能にしてしまう。はたして、「王政復古」という呼ばれることになった「明治維新」は近代日本の「正しい」始まりなのか、という脱神話的問題提起がここでなされているのである 私は子安氏の講義を聴き、神宮外苑の聖徳記念絵画館を見学したが、そこに掲げられた饒舌な説明の言葉に沈黙させられた。「明治維新に始まる近代国家日本の形成過程が明治天皇の聖なる事績として絵画化され、「壁画」群として展示されている」。日本人が希望をもって、これら「壁画」群を観るために集まる未来とはどういう未来だろうか。「壁画」群に、公=国家を超える天というものはみえない。薩長を中心とした「私」としての有力な封建的権力である連合反幕の運動が表象するものは、「明治維新」が「王政復古」であるという言説である。一方、武力的権力奪取(クーデター)に先行するかたちで、横井小楠の「天地公共の道理」において説かれたような、西欧と対等で自立した普遍性に依拠する別の言説が幕末に存在していたことが、次章にて論じられる。 子安氏は、「明治日本の帝国的国家形成を『王政復古』=『天皇親政』という歴史的理念の実現史として描き出す」「壁画」郡を、「『王政復古』と題されたスキャンダラスなクーデター的事件の始まりというべき場面の図」と分析している。 この「事件性を島田墨仙は岩倉具視の野卑な権謀家的風貌の上に表しているように私は思われる。その岩倉に正面して座する山内容堂の端然たる姿に画家はむしろこの歴史的事態における正しさを写し出しているようだ。」そして、「津田の明治維新をめぐる諸論によってはじめて、『王政復古』が武力討幕派の策謀によるクーデターであったことを、そしてこの事件が日本近代国家史の上に重大な刻印を強力に捺していったことを知ったのである。」つまり、津田にこのことを教えられるまで、子安氏は「王政復古」を「明治維新」と等置して疑うことはなかった、というのである。 「『維新』的近代の幻想」では、聖徳記念絵画館に端を発した、いわば、イメージの「王政復古」批判から、国史教科書の「王政復古」批判へと議論は展開され、昭和戦争時の国史教科書「初等科国史 下」(昭和十八年三月発行)の「明治の維新」章の「王政復古」についての記述が取り上げられる。そして、「この『国史』教科書は、聖徳記念絵画館とともに、『王政復古』=『天皇親政』的史観が昭和日本の制作物であることを告げている」ことを説き、「だが明治維新による日本の近代国家形成を『王政復古』=『天皇親政』的理念の実現と見るような史観は、一九四五年の皇国日本の敗北とともにはたして消滅したのだろうか。」という問いをわれわれに突きつけるのである。 戦後の日本人にとって「明治維新」とは何であったのか。子安氏によると、大学紛争は「近代の政治・社会制度的な遺物としてある大学の学問的制度的体系を解体的」に批判した。そして、生じた問題とは、「原理主義的性格を持った闘争」に導かれた学生たちの解体的批判が、内部抗争と暴力と自滅の末受けることとなる制圧ののちに起きた「合理的経営体であることを要求する大学改革」の結果、大学が持つべき抵抗する知という内部の力をも失わせてしまったのではなかったか、ということである。「明治維新150年」を迎えた現在、「明治維新」に始まる「この近代」そのものを問うことがない日本近代史家のような歴史家たちによって、ジャーナリズムとアカデミズムは「明治維新」を「蝶蝶と」語っているだけであるという。ネットに、「明治維新、万歳」の声もないが、「書店を賑わす明治維新関係書」は、この50年で大学の知の発する言説の質が変容したことを物語っていると言わざるを得ない、という。 津田左右吉によると、江戸時代は事実上の象徴天皇制だったという(徳川幕府が政治権力をもち、京都の天皇は文化権力をもっていた)。天皇が政治権力をもつのは王政復古というクーデターの明治維新からである。幕末に至って、「誤った勤王論が一世を風靡し、その結果、いわゆる王政復古が行われて、皇室を政治の世界にひき下ろし、天皇親政というが如き実現不可能な状態を外観上成立させ、したがってそれがために天皇と政府とを混同させ、そうしてかえって皇室と民衆とを隔離させるに至った」。子安氏は、「津田の反討幕派的維新観が党派的な非難をこえた根底的な批判を『王政復古』的明治専制政府と国政に向けてなされていることを知る」という。さらに、「昭和の天皇制ファシズムによる軍事的国家の成立を『王政復古』維新と無縁ではないと考える」子安氏は、「津田の維新をめぐる論考を大きな助けとして『明治維新一五〇年』を読み直したいと思っている。」という。つまり、昭和十年代の全体主義に帰結した「明治維新150年」の読み直しは、必然として、津田左右吉の「ラディカルモダニズム」の読み直しを必要とするのである。津田の思想が示唆する「もう一つの近代」に、現在の政治の行き詰まりを打破する論拠が存在するのである。
こうして、「『維新』的近代の幻想」は、思想史の自己像を示しているのであるが、フーコーは 「言葉と物」の書き出しにおいて思想史の肖像画について考えている。 「つまり、すでにしばしば彼(注、ベラスケス作の「侍女の間」の画家、つまり、言説を書く主体)の眼がたどってきた、そして疑いもなくただちにふたたびとるであろう方向 、いいかえれば、そのうえに、もはや決して消されないであろうひとつの肖像(注、王と画家自身との関係)がおそらくはずっと以前から、そしてこれからも描かれつづけ、描かれたままであるにちがいない、不動の画布の方向のことだ。」(「言葉と物」)
津田左右吉の永久革命的 な「ラディカルモダニズム」と和辻哲郎の国体的な「祀られる神は祀る神である」という思想は、思想史的言説を形成する双極をなす。知の考古学からみると、二つは対立する物の見方であるが、音声中心主義の論理平面からみると互いに補完し合い、言説の、言説上に構成される思想史の自己像の差異なのである。つまり、津田の「ラディカルモダニズム」と和辻の「国体論」とは、生と死における関係のように二項対立的に対立している。これらを脱構築するためには、思想史を言語平面に配置しなければならない。そうして、子安氏においては、江戸思想と後期水戸学において展開した制作論の視点から始まり思想史を読み直すことが要請された。そこで、明治維新の近代は、対抗西欧の近代とともに、荻生徂徠の命名制作論の祭祀国家の近代として、言説的に再構成される。また、開かれた文化である漢字文化圏の近代としてのアジアが、方法的に読み直されるのである。
「第二章 明治は始まりに英知を失った
横井小楠と『天地公共の道理』」
子安宣邦氏著「『維新』的近代
明治維新の近代を批判的に語ることができなくなってしまうのは、明治と江戸を分割することによって「言語の拡散」(
フーコー)が起きていることによるのではないか。五カ条の御誓文も拡散した言語としてだけ残っていて、もっぱら明治に確立したものの見方からのみ理解するため、意味がわからなくなる。
明治維新の近代を批判的に語るためには「言語の集中」(
フーコー)が必要となる。変革期におけるものの見方を知るためには、ここでは江戸のものの見方について考えなければならない。
明治維新に確立したものの見方のなかに、それとは異なるものの見方として
横井小楠の思想が見出せる。
横井小楠は、「長崎に来航した
プチャーチンとの交渉に」派遣された「
開明的な
幕臣」の
川路聖謨に書き送ったといわれる「夷虜応接大意」のなかで、
公武合体論を唱え、「有道無道を分かたず一切拒絶するは、天地公共の実理に暗くして、遂に信義を万国に失ふに至るもの必然の理也」と説いた。「信義をもって通信通商を要求することは公共の道理であってそれを拒む理由はない。『理非を分かたず一斉に外国を拒絶して必戦せんとする』過激攘夷派の主張は、
鎖国の旧習に泥み、公共の道理を知りえぬ必敗の徒の主張での思想である。」つまり、その思想は「
鎖国的な一国的割拠見」に依存するのではなく「変革期の基準として機能する理念」であると子安氏は読み解く。「天地公共の道理」の言説は、
薩長の各藩が勝手に戦い自分の軍事力を高める一国的割拠を否定するものである。私には、これは
伊藤仁斎の
朱子の克己復礼の教説を
脱構築的に注釈したものにみえる。
横井小楠は天下的公の
儒者であり、その「
儒者的英知」によって「グローバルな視圏の拡大」が可能となる「精神の器量」がもたらされた。
彼に、「幕府諸藩の体制維持に収斂する政治的思考と行為とを『私事』『私営』と断ずる」普遍的な公共の視点をもたらしたのは、幕府によって広められ文明論的展開をもたらした書物の「海国図志」であった。ここで、子安氏は、彼の「
実学」が道徳的内面性に裏打ちされ、変革期におけるものであることを見逃さない。私には、変革期における道徳的内面性が、自らの中に閉じてしまうことを許さない天地公共の明確なイメージを持つ必要を促した、とみえる。こうして、われわれが
横井小楠を考えるとき、早すぎた近代の超克に行きつかざるを得ないのである。
天保8年(1837年)下総
利根川畔の農村に生まれ、
明治4年に35歳で逝った
鈴木雅之は「遅れて発見される
国学者」である。ちなみに、
鈴木雅之の名前をネットで検索してもほとんど情報を得ることができないのが現状である。子安氏は「農村の生んだー
国学者」である
鈴木雅之が著した「撞賢木」の「総説」より次の言葉を引く。
「凡そ世(世界)になりとなる(生々)万物(人は更なり、禽獣虫魚にいたるまですべて有生のたぐひ)尽く、皆道によりて生り出づ(道のことは下にいへり)。道ある故に、世にある万物は生り出たるものなり。」
「人もとより道を行ふによりていけるなり。いける故に道を行ふと思ふは、反(かえ)ざまの惑いなり。(人此の惑ひある故に道と疎くなりて、ややもすればはなればなれになるなり。人と道とは然はなればなれになるものにはあらず。道を全く行ひ得ると行ひ得ずしてかくものとはあれども、いけるかぎりのものは、たれも皆しらず行ひてあるなり。全く道を棄絶ていけるものは、更にあることなし。)」
そして、子安氏は、「生成の道の根元性をいい、地上の生活者をその生活による道の遂行者」であるとする「生活者の思想」に行き着き、「(平田)篤胤ら
国学の先達に」回答を与えた、この農村の「異様な向学心をもった少年」、「異常の一少年」に驚き、「同時にこの少年を生み育てた江戸後期下総の一農村に驚くのである」。
江戸時代の「参勤交代が作り出す政治的な全国的ネットワークは、同時に経済的ネットワークをなし、文化的ネットワークをも構成した。さらに
幕藩体制社会にとって重要なのは都市と農村とのネットワークである」、「
儒学や
国学、
蘭学、心学などなどがこのネットワークによって全国的な学派、門流を成していった。ことに一八世紀後期から一九世紀初頭の江戸社会にあって、江戸と地方農村の
豪農層を通じてのネットワークの形成とこのネットワークによる著述の販売と教勢の拡大を意欲的にはかったのは
平田篤胤とその学派的中心気吹舎(いぶきのや)であった」。
鈴木雅之は生成の道の根元性から、ネットワークとしてグローバルに繋がる活動性の意義を考えた。ネットワークを語るのは、文化的ネットワークに依拠して学んだ彼の経験による所が大きいのではないだろうか。
ここには、近世江戸社会に脱階級的な知識・学問が展開と普及をなし、書物の存在が自発的学びを創り出し、多孔性のネットワークとして発展していた状況がみえる。子安氏は、60年代の終わりの時期に、「日本の名著」(
中央公論社)の一冊としてとして「
平田篤胤」の巻の構成と解説の仕事に取り組み、篤胤の「
霊能真柱」を軸に、
佐藤信淵の「鎔化育論」と
鈴木雅之の「撞賢木」を添えて、「
国学的
コスモロジーとその展開」をテーマとすることを構想する。
「<外部性>という思想的テキスト解読のための方法的視点を自ずから私はドイツ滞在によってもったのである。ドイツから読むことによってはじめて私が顕幽二元論的構成をもち、救済論的課題を内包した篤胤
コスモロジーの意味を読み出すことができたのである。やがてそれは
ポスト構造主義的なデイスクール分析の方法として80年代以降の私の思想史を導くことになる」。
「このドイツ滞在は私に篤胤を再発見させただけではない。
鈴木雅之という農民思想家を発見させたのである」。
鈴木雅之を発見することの意義は、この章の最後の子安氏の言葉に集約されている。
「国家的神(現人神)の原理によって丸ごと作り上げていった近代日本は、」「生活者の思想をうもれさせることによってその国家的運命を遂げていったのである」。
「第四章 形は直ちに心と知るべし 梅岩心学をどう読むべきなのか」
江戸の武士政権によって、
天皇・貴族・寺社が独占してきた学問にアクセスできるようになった農民や町人の中から、心学とその運動を創始した
石田梅岩(1685‐1744)のように、
形而上学を構築するものが出てきた。こうして、17世紀にアジアの知識革命が起きたといえる。これは特筆すべきことである。しかし、この「学び」の脱階級的な意義を明治国家と
和辻哲郎の人倫国家は理解しなかった。その理由は何であろうか。
この問いには、なぜ「
明治維新の近代」の考察で
石田梅岩を取り上げるのか、という問いが答え得る。近代は、前近代をして自己を実現するぐらいのものとしか考えないが、これは自己正当化の認識のとんでもない傲慢かもしれない。
例えば、
薩長の王政復古のクーデターによって
天皇にすべての権力を集中させて成り立った
明治維新の近代は、江戸時代の理想を実現することに失敗した、と考えてみたらどうだろうか。実際、
明治維新は新権門体制を確立して不平等を拡大させたのではなかったか。では、江戸時代の理想とは何か。差別のない世の中という理想である。一方、同時代の西欧のように差別を無くしていく社会的方法を具体的に論じることは、政治権力をもつ武士政権を批判する危険な行いであったから、商人出身の
伊藤仁斎はそれを道徳的に議論した。また、
形而上学的に平等とその意味を考えたのが、農民・商人出身の
石田梅岩であった。江戸という時代は商人と農民が学問をした時代である。特権階級である
天皇・貴族・寺社から奪った学問を、武士は商人と農民に与えたのである。
農家に生まれて、京都の商家へ奉公に出された後に心学を創始した
石田梅岩は、「形は直ちに心と知るべし」と説く。ここでいう「形」とは、「真の<人間的平等>への心学的苦闘」を続けた
石田梅岩が、商人の人間的・倫理的価値主体の確立を意図したときに出てきた概念であり、「社会的存在としての人の具体性」をいう。「その存在の具体性において、その存在に求められている行為を端的になすことを『形ヲ践(ふ)』むというのである。」そして、「心ノ工夫」という精神をいうことによって、「現に、<形>としてある自己を、自然必然的な存在と観ずる自己否定の能動性が、その<形>に対応する<則>を没我的に遂行する主体、一個の倫理的主体を成立させるのである」。
朱子は「気が直ちに道理だ」と言った。つまり、形とは、具体的な存在のあり方であり、天から与えられた、と子安氏は読む。
伊藤仁斎のように、(ただし
朱子の思想的枠組みを棄てることなく)
石田梅岩も
朱子の「克己復礼」を彼なりに解釈したらしい。「形は直ちに心と知るべし」は目覚めの契機を指示しているのが、その心学の面白さである。
「武士的主従関係における献身的な<臣>のあり方を一般化し、『総ジテ重モ軽モ人ニ事ル者ハ臣ナリ』と商人の実践的な主体のあり方をも<臣>ととらえるのである。そしてかく商人を<臣>ととらえることによって、献身的な臣の能動性と倫理性とを商人的主体に保持せしめようとするのである。」
「私がここに見ようとするのは、この<心学>としてはじめてなしえた商人の人間的価値主義の確立である」。
「梅岩が商工業者を『市井ノ臣』ととらえたことはよく知られている」。
「梅岩は
士農工商をいずれも<臣>ととらえ、商人が臣として相事するのは<天下>であるという」。
ここで、子安氏は
葉隠の武士道のパトス(家光の死以降殉死が禁止される)に注意を促す。武士道のパトスの知が商業の取引の場で実現していくのではないかというのである。ここで、パトスが武士から商人へ移動する関係のダイナミズムを観察できるかもしれない。「君ニ事(つかえまつ)ルヲ奉公ト云、奉公ハ我身ヲ君ニ任セテ忘レタルナリ」(『石田先生語録』巻八)という献身の忘我性の強調は、武士と商人の間に共通のパトスがあることを読み取ることができる。