
廣松の『ドイツイデオロギー』の文献的解明がどうしてそれほど大事なことなのかよくわからない。イエニーのことも触れるが、まるでブルジョア作家が「忠実な」妻にタイピングさせたぐらいのことでしょうと言っているようなものだった。結局彼がやっていることは、テクストの不透明性を取り去る方向ではないのかともおもう。『資本論』にイエニーがどれくらい介入したかという問題は無視できない重要性がある。フェミニズムのロンドンはこれを問うことになった。その戯曲を書いたアイルランドでは、主人のデイスクールに従属したイエニーは、イギリスの知に従属してきたアイルランドの主体のあり方を考えさせるものである。マルクスとエンゲルス、イエニーについてその錯綜した関係を小説にできないだろうかと、ロンドンのイスラエル系ユダヤ人に話すと、さっそく三者の星座の位置関係を調べあげて、色々話しはじめた。隣で、彼のカバラ的謎解きに胡散臭さを感じたナイジェリア人に、文章を書いていると、毎晩天井から足音が聞こえはじめた、イエニーではないかと告げると、震え上がった。だがユダヤ人をみると彼は幽霊に全く関心がない。専ら解釈するだけ。ナイジェリア人は商品の分析を受け入れることができない。彼らはユダヤ人商人によって奴隷として売られていたからだ。「交通」のコンセプトを作ったって?マルクスもユダヤ人じゃないか、「交通」で交換された奴隷の歴史をどう考えていたのか。おまえたちは人間性を失っている。商品の分析をもって一体何がみえてくるというのか。と、激しい言い争いがはじまった。だけれどユダヤ人もナイジェリア人も、ヨーロッパ帝国主義の支配の歴史に対する批判を共有できるから、ヨーロッパにおけるユダヤ人排除の歴史から、アフリカから、イエニーの立場がどういうものであるかわかるので「マルクスの貢献者」などという形で彼女の名前を消し去ってはいけないと理解できるのだ。このことだけはたしかである。結局わたしのどのような言葉もただちに分裂し、『資本論』を書く戯曲の注釈は彼らの注釈によって二重化されていった。ここで、『言葉と物』のフーコの言葉をひきたい。
監督の1968年をどうみるかという視点がいかに、1840年代に反映されているのか?映画は、フェミニズムの演劇が先行しなければ、イェニーにマルクスが意見を求める場面をもたなかっただろう。経済革命なき政治革命には、政治革命なき経済革命にもまた、青年マルクスからみると思想革命が無い。マルクスは『貧困の哲学』のプルードンのために『哲学の貧困』を書き、イギリス労働組織委員メンバーにたいして蜂起の思想的根拠を問う。だけれど思想の内容がなにであれ、言論の弾圧を受けたマルクス、エンゲルス、イェニー、プルードンを自由に喋らせた当時のパリは、多孔性ともいうべきその不透明なものとの出会いを可能にした空間をもっていた。政治的亡命者を受け入れていながら、集会で代表として承認された壇上のエンゲルスが彼が称えるそのマルクスの本を読み上げたり、エンゲルスがイェニーにマルクスが書いた文を正しく読ませるというロンドンとの違いは何だろうか?
知ることとは言語を言語に関係づけることである。語と物との画一的な平原を復活させることである。それはあらゆるものを語らせること、いいかえれば、あらゆる標識のうえに注釈という第二の言説を生じさせることにほかならない。知に固有なものは、見ることでも、証明することでもなく、解釈することなのだ。
あれから10年たった。たしかに、テンソルについて分析されるほどの‘トータルな認識‘の地平とされたけど、ヨーロッパの思想をよく知っていたけれど、支配されたアジアの思想家(竹内)が近代の超克をどう語っていたか知らないようでは、廣松はそれほどトータルではなかったのね。アジアの声なき声をきかなかったのだから、抑圧された他者であったイエニーは存在しなかったのだろう。
ポストモダンの時代に真実を考えることの意味は何か?
形而上学は存在を存在として考えることの意味を問う。17世紀が読み解くアジアの形而上学の始まり(13世紀)に、すべてを語り尽くすと語る主体が登場する。それは、近代の真実を自己が話し自己が聞くという主体の体制の先駆を為すようにみえる。さてポストモダンの時代に真実を考えることの意味は何か? 近代の魂で考える<一>と異なって、ポストモダンの<多>は思考される身体を考える。近代は、語る主体は存在するから存在するとする。ポストモダンは、語る主体は言説の語る主体が存在するから存在すると考えてみようとする。他者が住処とする存在の多義性が語り出されて行くのは、二つの身体の間の投射からである。投射によって規則的なものー言説の配置ーが成り立つ。二つの身体の間を引く線、語る主体(自己同一性)の線、それから逸れる(差異化の)線、これらが言説の配置を形成していく
そもそもデモクラシーとは、民主主義的人間が固有の性格をもたないのと同様、政体ではないのだ
ー デリダ『散種』
大きな他者とはなにか?「わが国には有史以来3000年の歴史があります」「エジプトの方が少しだけ古い」「しかし唯一連綿と続く文明が中国です」はなにを意味しているのか?これは、近代以降等しく諸言語(ラング)の洪水を被っているにも関わらず、つまり音声化の方向にすすんでいるのに、まだ自己だけは、連綿と漢字エクリチュールの絶対的優位を保っていると誤解している帝国の思想だろう。アジアを支配した書かれた言葉の象徴性。厄介なことに、大きな他者はそれによってナショナリズムの混乱を免れているとおもいこむとしたらそれは新しいナショナリズムの発明かもしれない。この大きな他者があっという間に現れたことにたいして、周辺国はこれとどう折り合いをつけるのかが大変難しいと言われたが、同様に、大きな他者の内部の国々にとっても難しくなってきたようである
ポストモダンにおける差異の肯定も、モダンにおける差異の否定(つまり否定の差異)も、「哲学の根本問題」の思考において、分節化されることが無いのよね、このことが西田において理解されていないというか、もちろん理解しているのだろうが、読者に対してあえて全然問題にしない戦略をとるー わたしの理解の限界を超えるのでなければ。せっかく複雑で透明でない<他者>を、なぜ、単純で透明な<我と汝>にしてしまうのか?この「哲学の根本問題」を問題にすることこそが「哲学の根本問題」である。
ところで表現の自由をいうのなら、世の中にポストモダンの思想史を書くスペースがなくなったというこの問題を考えてみる必要があるかもしれない。そもそもポストモダンにおける「脱近代」の「脱」は破壊の「反」の意に理解されたところから間違えたんじゃないか。破壊の反近代と言っても、それが対抗する近代は永久革命をもっているから、おなじ否定の差異化と言わざるをえない。諸言語のナショナリズム、これは、16世紀の第一次的パロールの絶対性の喪失(近代におけるバベルの災厄)がもたらした混乱である。「脱近代」は、否定の差異化をおしすすめていく音声中心主義のラジカルモダニズムを脱構築する。ヨーロッパでもアジアでも、どこでも、差異を肯定していくエクリチュール的運動の思想史的事件性が問われているのだけれど。しかし現在は、差異の肯定の脱近代は否定の差異の近代によって包摂されてしまったといおうとする時代なのだろうか、すでに言われたことをはじめて語るように..
ヴィットゲンシュタインはアイルランドに二年間ほどきている。なぜアイルランドに?長年研究者の間では、ほんとうのところ、ロンドンから離れて愛人と会いにいったというぐらいの関心しかなかったようである。アイルランドは研究するに値しないのだ。50年代は一番ヤバかった閉鎖的な時代といわれる。わたしの友人の画家は当時息苦しさのあまり街頭に踊り狂う人々をみている。この国でヴィットゲンシュタインは驚くたくさんの数の遺書を書いている。ダブリンでは一日中河を見ていたというメイドの証言がある。「ハムレットもノルウエーに帰る途中でアイルランドに寄ったためにああなっちゃったのかもしれない...ウィットゲンシュタインもなあ」とダブリンの詩人がわたしに語ってくれた。彼は言う。「西へ行け」と。ヴィットゲンシュタインが行った西の方は荒涼とした未開発の地域がある。ここに彼は小屋を建てた。現在ここらあたりに立つと、単純すぎて、視線は物の輪郭を捉えることなく彷徨う。なんか物語も意味も消滅するというか、だからかもしれないが、フレームも光量も定まらない。ジョン・フォードが撮影したようにはいかないのである。いったい眼のまえに何が存在する?と疑うまえに、見ることそれ自身を疑ってしまう。具合が悪くなる。見なければやっていけないとしたら、見ることは要請なのだ。だからキャメラは命題論理であり得る。
ウィットゲンシュタインについてはこの十年間覚え書きばかり書いていた。エクリチュール(の毒)によって、アイルランド人がウィットゲンシュタインをどうみていたかとする見方を考えた記憶を眠らせる必要があった。ウィットゲンシュタインは記憶のウィットゲンシュタインではなく、エクリチュールのウィットゲンシュタインである。毒は薬なりという話もある?エクリチュールという記憶の外部は記憶にとって毒であるというようなことをデリダが言っている
エクリチュールは(内在的)記憶に対して外在的であるにもかかわらず、ヒュポムネーシス(覚え書き)は記憶ではないにもかかわらず、それでもエクリチュールは記憶に影響を及ぼし、記憶の内部において記憶を魅了し、記憶に催眠術をかける。これがかのパルマコンの効果である。(『散種』)
将来誰もが避難所から受け入れて貰えぬ立場になり得る暗黒の不確実性の時代だからこそ、誰も避難所から受け入れて貰える平等を保障した社会契約を再構成したほうがいいんじゃない?
何人も、自己のまわりに、明治維新の近代国家に先行した漢字と仮名をもつ権利を奪われない。そうでなければグローバル・デモクラシーの言語のあり方を考えることができなくなるから
有機的だから生命があるのか?否、非有機的であるからこそ強度をもった生命というものがある。このような平面をどう構成するかはどんな線を描くかによる。非表象から表象へいく線は外部をもたない。逆に、表象から非表象へいく線は外部が介入するときである。外部とは、なにか、目に見えない多分詩と舞台で成り立っているチェス盤のページなのではないかしら?見えない白紙の本
Le Maître dit: < Le sommet de la sagesse est d'éviter le siècle; puis, d'éviter certains pays; puis, d'éviter certains gestes; puis, d'éviter certains mots.>
Le Maître dit : < Sept hommes l'ont fait.>
( Confucius, Les Entretiens)
子曰、質勝文、則野。文勝質、則史。文質彬彬、然後君子。
「子曰く、質、文に勝てば則ち野なり。文、質に勝てば則ち史なり。文質彬彬(ひんぴん)として、然る後に君子なり」(『論語』)
フランス語訳を示すと、Le Maître dit; < Quand le naturel l'emporte sur la culture, cela donne un sauvage; quand la culture l'importe sur le nature, cela donne un pédant.L'exact équilibre du naturel et de la culture produit l'honnête homme.> ー Confucius, Les Entretiens
吉川のように、文明(「文」)と素朴(「質」)の構造的対概念を以て、理想化された人間を表象するようではオリエンタリズムに陥る危険がある。シナ学の背景をもつフランス語訳に、la culture と le nature の二項対立をみることができる。
そこで、子安『思想史家が読む論語』は、質を「人間の具える天賦の自然性」として捉えた上で、人間にとって大事なもう一つの要素があるのではないかと問う。「それが文である」という。ここで、人と、人が学ぶ先人が遺す文章との関係が問われていると説明されるのである。私の理解が間違っていなければ、仁斎にとって最大の関心は「人」である。人が人として成り立つためんなは、絶えず天賦の自然性と原初的エクリチュールに立ちもどっていく必要がある。卑近に、自分のまわりに、漢字をおく必要があるだろう。だからこそ、何人も、自己のまわりに、明治維新の近代国家に先行した漢字と仮名をもつ権利を奪われないと私はおもう。そうでなければグローバル・デモクラシーの言語のあり方を考えることができなくなるから。
また、答えることのできぬ問いを開くために、「行いて余力あらば、則ち以て文を学ぶ」、「博く文を学ぶ」という(『思想史家が読む論語』)
ある年アメリカからはいってきた原理主義の影響で聖書入門がなんと英国のベストセラーになった。左翼は危険に考えた。だがこのときジジェクは聖書を読めとロンドンの聴衆にすすめた。敵をやっつける方法がちゃんと書いてある。ユダヤ人たちは徴にこだわったのだと。おなじように、『古事記』を読めばいいのかもしれない。「神」をカミと呼ぶかシンと呼ぶかはわからぬが、伊勢神宮は憲法より上にあると主張する日本会議には、「統治権をお願いします、その前に、神の末裔である天皇から統治権を委ねられたとする証拠の三種の神器を見せてください」と言えばいいのである。なにか?
海外に行くとかならず三島についてきかれる。大江についても。戦後文学はなにかを観念化しているー指摘されるように、敗戦後の日本人がはじめて罪悪感を持ったことを観念化した?三島も何かを観念化したからこそ彼について聞かれるのである。村上を読むひとは彼についてきいてこない。多分彼はなにも観念化してはいないのだろう。海外で私も三島についてきかれたとき 最初に読んだ小説が『金閣寺』だったが、積極的に語る気がしなかった。三島を語るのは面白くないから、語る気がしない理由のほうを考えたほうがいい。だが中々わからない。今なら少し考えられるかな。三島は、失敗と考えられた(?)明治維新の近代を完成させるためにアメリカとの戦争に勝たなければならないと再び大衆に訴えることによって戦争を観念化する意味があるとかんがえたとしても、なんで不格好にあんな形でしか実現できなかったのかね?
French utopian socialism + English political economy + German idealist philosophy = 0
映画は亡霊をみせるのだろうか?マルクスも亡霊を断ち切りたかった。彼の心の中で妻は理解せずに亡霊が定位する文字を追ったか?亡霊と交信するのはエンゲルスである
Il est besoin d’une marque visible des analogies invisibles
ー Foucault La pose du monde
目に見えぬ類比の目に見える標識が必要なのだ。
ーフーコ『言葉と物』世界という散文
五反田の喫茶店にて飾られている英語の本たちを棚からかってに取りだして読んでいる。1970年代に出た本があつまっている。と、25歳ぐらいのお姉さん二人が隣に座った。世の中に不満をたくさんもっている。台風の話の後、「日本なんかなくなればいい」と呟いた。日本の未来を憂いている。おじさんが物語る全知全能のシナリオ話と違って、感情を表出しているのがいい。そこでフクロウ猫は、「お嬢さん、暇というのは、どんなに暇でも、日本の未来を語るほど暇ではないのです」と加わろうとしたが、ネットの空間でもないのでやめたのであった...
昼の本と夜の本
昼の本は本それ自身ではない
両者の間に共通なものがない
そこから夜の本がはじまる
線が一本の糸の点の繋がりとなり
点は線となる。面は光の方向となり
言葉は見えず暗闇となる
沈黙が言説の煌めきを眠らせるとき
死に場所が奪われた。民族根絶の目的の為に先祖代々の墓を強制取り壊すことほど、文明論的同一化と開発と戦争をやめぬ近代の永久革命を表しているものはないのではないかとおもう。それにしても中国である香港が自己決定権を求めて中国共産党批判を行っているというのにだよ、中国でない日本においては中国共産党批判の拘束が中国よりも厳しいのは一体これはどんな国だろうか?
Il n'est pas lui-même au centre, occupé par la machine, mais sur le bord, sans identité fixe, toujours décentré , conclu des étas par lesquel il passe. Ainsi les boucles tracées par l'innommable, <tantôt brusques et brèves, comme valsées, tantôt d'une ampleur de parabole>... Bien plus, l'œuvre d'art est machine désirante elle-même.l'artiste amasse son trésor pour une proche explosion, et c'est pouquoi il trouve que les destructions, vraiment, ne viennent pas assez vite.
ーDeleuze=Guatteri Anti-Oedipus
ルソーの『孤独な散歩者の夢想』「第五の散歩」では、魂の秘密や物と身体との境界で生まれる印象に対して、ランガージュがおのずから透明となっている。-言葉と物-
注釈を超える注釈とはなにか?
先ず本居宣長が行ったのは神話の注釈である。神の道を解釈した。そこで宣長は体言と用言をめぐる中国語と日本語との言語的差異に注目している。つまり言語の注釈も行なっていたということができる。子安先生は、宣長は「神」を敢えて「シン」と読むことによって何をしたかったのかを問う。宣長は、朱子学(理気論と鬼神論)の言説から、言葉を奪回して、中国文明から自立するための思想を注釈のなかに書いている。つまりこれが注釈を超える注釈をなすものである。問題は、漢字なくして思想は可能だろうかというこの一点にある。あるいはロゴスは成り立つのか?もし可能でないとしたら、または成立しないとしたら、漢字は思想にとって不可避の他者と考えざるを得ないとおもわれるが、そうだろうか。こうした問題提起は子安先生が独自に打ちたてたものであるが、きちんとどうかんがえるのかが先月から始まった『国学における「神」の成立ー本居宣長の「神」の注釈』において明らかにされることになるだろう
映画のなかの黒板
スクリーンと黒板は互いに似ていたことに驚きます。世界という散文のなかで、目に見えぬ類比の目に見える標識が必要なのです。これほど類似しているのは、多分鏡が媒介しているのでしょう。とはいえ、わたしはまだ鏡というものを見たことがなく、毎朝鏡を見ずに髭を剃っているのですけれど。どちらが相手よりもより大きい鏡なのかはわかりませんが、類似している限りでの相似の形式であって、自己自身に含まれるという意味における同一の形式にあらず。発見されなければスクリーンと黒板との類似性は秘密のまま眠ったままです
「恩赦」の制度にも、祈る天皇に感謝せよとはね、ヤレヤレ、まるで共同幻想の島の「土人」に教えてくるみたいだ。これは国家祭祀の天皇を批判しなかった、実は構造主義でしかなかった吉本隆明に遡る言説なのか?『最後の親鸞』という立派な仕事もあったのだけれど、吉本信者だけで天皇教に感謝しなよ。
16世紀は類似というものが知の役割を演じていた時代であった。世の中はまだ類似物で構成されているに違いないが、それはマイナーな知である。たとえば生まれ変わりの伝説は類似の想像力だろうが、それは近代における知の中心をしめない。知の周縁を為すものでしかない。その周縁にある映画においては類似というものがまだ大切な役割をもっている。20世紀後半に現れた映画史においては映画それ自身が類似物である。現代は現実が映画に似てきたのでーかつては俳優が政治家を真似したが、現在は政治家が俳優を真似しているー、再び類似というものの意味がかんがえられることになってきた。さて彼らがまったく知らないパゾリーニの映画でもそのスチール写真を見せれば若い人は「ホラーですね」と言う。驚いた。わたしは「ホラー」の意味がわからないが、たぶん何かと似ていることは似ているが、パロールでは捉え切れない過剰があるということなのだろうか。標識は読まれるのを待つ記号である。見つけたら過去が目覚める。そして認識する作用によって、認識される過去が不動のままにあることはあり得ない。かつて映画とはそういうものだった。そこで表現されている世の中はおなじではありえないのであった。映画が消滅した日がきても、鏡が時間に定位しているのだから、徴は至る所に存在する。徴を見つけることができなければ、あるいは見つけたとしても解釈できなければ、類似によって成り立つ、世界という散文は化石として眠り続ける。
普通選挙と文化多元主義と権力分立の危機のなかであらわれてきた日本人という単一民族の幻想、ある国家でしかないのに日本国家しかないとする幻想(「ラグビーは日本を応援するのは当然でしょう?」という言説)。これらのことは、近代が自ら、国家の宗教性に折り重なることによって成り立ったというところに原因があるんじゃないかな。日本近代の場合、水戸学後期の政治神学の問題をかんがえる必要がある。形而上学に取り組む問題かもしれない。近代を問うたヘーゲルが言ったようには国家は宗教の超越性を禁じた(乗り越えた)のではなくて、国家がやったことは国家の宗教性をもって宗教に置き換えたというかね。国家の宗教は、マルクスが見抜いたように国家は他者排除によって成立した以上、永久革命的に、隣人を大切にする人類愛の信の構造を抑圧していく宗教性をもつ。 普通選挙と文化多元主義と権力分立の危機のなかであらわれてきた日本人という単一民族の幻想、ある国家でしかないのに日本国家しかないとする幻想(「ラグビーは日本を応援するのは当然でしょう?」という言説)。これらのことは、近代が自ら、国家の宗教性に折り重なることによって成り立ったというところに原因があるんじゃないかな。日本近代の場合、水戸学後期の政治神学の問題をかんがえる必要がある。形而上学的に取り組む問題かもしれない。近代を問うたヘーゲルが言ったようには国家は宗教の超越性を禁じたのではなくて、国家は国家の宗教性をもって世界宗教に置き換えた。国家の宗教は、マルクスが見抜いたように国家は他者排除によって成立した以上、永久革命的に、隣人を大切にする人類愛の信の構造を抑圧する宗教性をもつのである。 国家の宗教性は、それに抵抗するそれほど透明でない異質性の政治を透明なものに還元して否定し尽くす。そこに固有性の偶像を錯視する危険があるのではないか
グレコ。16世紀における芸術の外部へ出る力は、危機の17世紀に先行したのではなかったかをかんがえさせる...
13世紀から江戸時代まで、即位礼では、密教の考え方にもとづく「即位灌頂」が行われていた。天皇は高御座で、二条家から教えられた印相を結び、真言を唱えた。(島田)




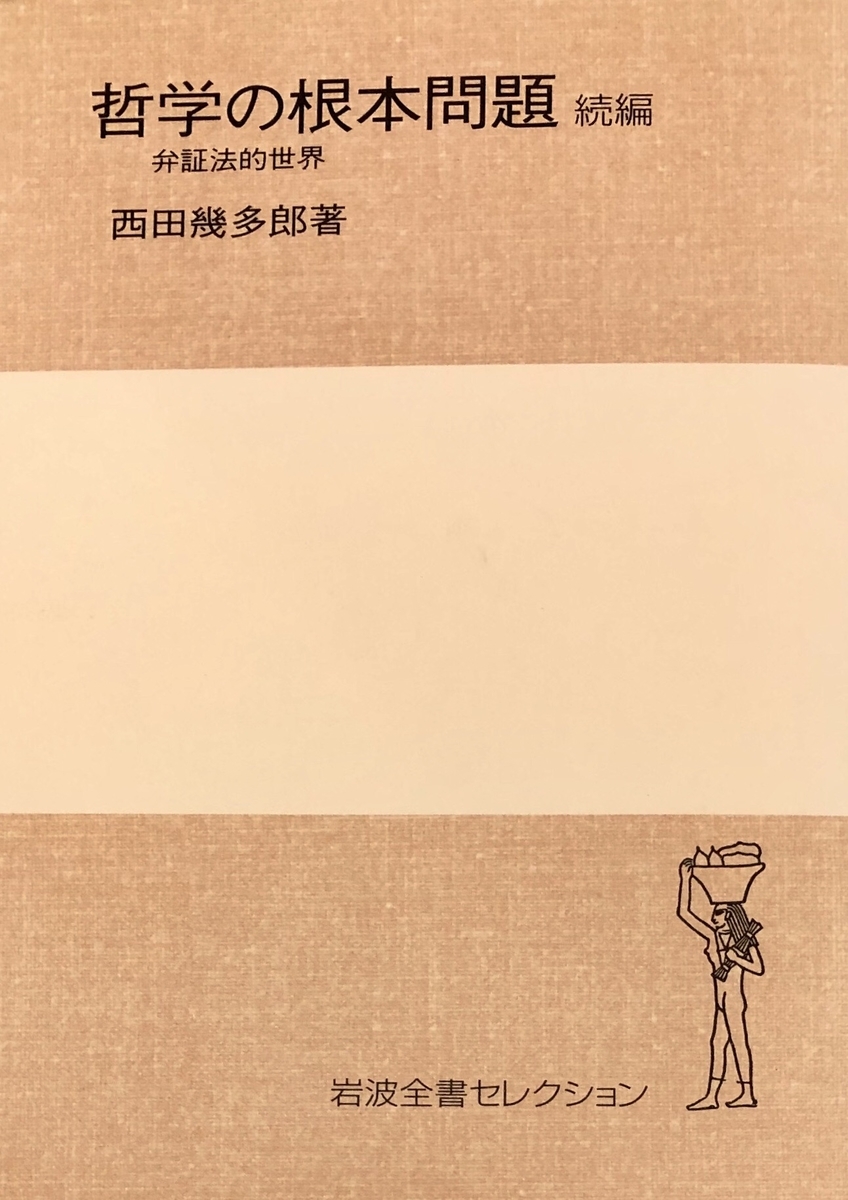 の
の